|

1999年9月ダイオキシン対策関係官僚会議で一般廃棄物は5%を削減、産業廃棄物は増加率を13%に抑制し、2010年までに1996年度比で半減させることを柱とするゴミ減量の目標値が確定されました。具体的な目標値が政府によって示されたのは始めてで、更に排出量削減の一方でリサイクル率を1996年度の10%から24%に引き上げることになりました。早くから環境対策に取り組んでいた企業や施設がある一方で、ようやく対応を始めたところもあるなどまちまちですが、法制化への流れを受けて、環境への取り組みは急ピッチで進んでいます。
こうした中で、生ゴミ処理技術が注目を集めています。生ゴミ処理技術は、生ゴミを微生物で分解、脱水、圧縮、冷凍、焼却、乾燥等して処理します。企業の廃棄物削減への取り組みがされる中で、業務用生ゴミ処理機市場は大きく成長しつつあります。大規模施設向けからコンビニエンスストアなどにも適した小型機まで多様な機械が登場しています。
 これまで食品工場や大型飲食店、病院、百貨店、市場、ホテル、学校給食センターなどの大規模施設では廃棄物処理業者に委託したり焼却により自家処理することが多くありました。それが外部にゴミ等を排出しないというゼロエミッションの考え方の浸透や、焼却の際に発生するダイオキシンの規制強化から生ゴミ処理機を導入する気運が高まってきました。 これまで食品工場や大型飲食店、病院、百貨店、市場、ホテル、学校給食センターなどの大規模施設では廃棄物処理業者に委託したり焼却により自家処理することが多くありました。それが外部にゴミ等を排出しないというゼロエミッションの考え方の浸透や、焼却の際に発生するダイオキシンの規制強化から生ゴミ処理機を導入する気運が高まってきました。
その背景には、企業が環境への社会的責任を果たすとともに、イメージアップにもつながる環境保全に関する国際規格ISO14000シリーズへの対応があります。また、廃棄物減量化目標の設定や生ゴミを含む事業系一般廃棄物の排出者責任の強化など、廃棄物処理法が進められつつあることも背景の一つです。
農水省は食品メーカー、流通業、外食産業等食品関連産業が出すゴミのリサイクル推進を盛り込んだ「食品産業の環境対策ビジョン」をこのほど作成しました。製造過程で出るカスや、外食店の食べ残し等食品廃棄物を飼料や肥料にして再利用することを提言しています。
学識経験者らによる検討委員会を設け、法規制も視野に入れた具体策が検討されています。年間発生する生ゴミは3千万tといわれ、そのうち賞味期限切れ食品や調理くず、食べ残し等の食品廃棄物は1800万tと一般廃棄物の3割を占める。その殆どは焼却処理されており、事業者の負担が重い上に環境の影響も大きい。焼却処理はダイオキシン発生の問題もあって、焼却量の削減はもとより、焼却処理しなくても済むリサイクルへの対応が求められています。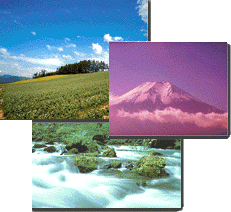
個人にとっても企業を最終的に廃棄物とするのではなく、自然の物質循環サイクルの中で再資源していくことは、文字通り自然との共生を無理なく可能にしていくことです。有機性資源(生ゴミ)から作った再生品の流通が、資源循環のネックとなっています。例えば有機性資源(一般ゴミ)から作ったゴミ固形燃料(RDF)、ゴミを破砕、圧縮成型してペレットに加工、発電などの燃料として使う仕組みです。 そこで、大きな問題となったのがゴミ固形燃料(RDF)の流通。燃料として不安定なことに加え、製造コストが高いことから引き取り手が見つからず、再度ゴミとして捨てられているケースも発生、普及にブレーキがかかりました。一方、企業、自治体へのリサイクル規制は強まる、ゴミをただ再生する「再資源化」だけでなく、「再生品の流通」まで含めた体制をとることが、リサイクルを実現する上で不可欠の問題になってきました。
※「日本経済新聞」より抜粋
|